
こんにちは。
中国輸入OEMマスター龍です😀
輸入ビジネスを始めたばかりの頃は、アパレルや日用品といった参入しやすい商材からスタートする方が多いものです。
しかし、この分野は競合が非常に多く、利益を出し続けるのが難しくなるのも事実です。
ある程度輸入の流れに慣れてきたら、思い切ってライバルが少ない商材にも挑戦してみるのがおすすめです。
その一例が「おもちゃ」です。
特に乳幼児向けのおもちゃは、安全面の規制が厳しく、
日本への輸入には食品衛生法に基づく審査と届出が必要となる場合があります。
わずかA4一枚の申請書ですが、この手続きをきちんと理解しているかどうかで、
輸入の可否やスムーズさが大きく変わってきます。
なお、個人で使う少量のおもちゃであれば届出は不要で問題なく輸入できます。
ただし、数量が多いと税関で「商用目的」とみなされる可能性が高くなり、
届出や審査を求められることがあるので注意が必要です。
コンテンツ
中国からおもちゃを輸入する際に注意すべき規制とは

中国からおもちゃを輸入するメリットは、コストを抑えられるだけでなく、
日本では見かけないユニークなデザインの商品を仕入れられる点にあります。
そのため、多くの輸入事業者にとって魅力的な市場となっているのは間違いありません。
しかし、どんなおもちゃでも自由に輸入できるわけではありません。
中には食品衛生法の規制対象となる商品があり、
輸入時には特別な手続きや審査が求められるケースもあります。
食品衛生法は消費者の健康を守るために制定された法律で、
玩具に使われる素材や製造工程に関する安全基準を細かく定めています。
特に対象年齢が6歳未満の乳幼児向けおもちゃでは、子どもが口に入れてしまうリスクもあるため、
有害物質の混入を防ぐために非常に厳しい基準が設けられています。
そのため輸入者は、事前にこれらの規制を正しく理解し、
必要に応じて製品の検査や認証を行うことが不可欠です。
もし基準を満たさない製品を輸入すれば、法律違反として罰則を受ける可能性もあるため、
信頼できるサプライヤーと取引することが求められます。
こうした法規制をしっかり把握しておけば、安全でスムーズな輸入取引が実現できます。
なお、ここで説明しているのは商用目的の場合です。
個人が自分で使用する分に関しては規制の対象外となり、自己責任で輸入することが可能です。
下記に食品衛生法についての記事をまとめましたのでご確認下さい。

【保存版】食器・玩具の中国輸入|食品等輸入届出手続きと食品衛生法の完全ガイド
規制対象の「指定おもちゃ」:例
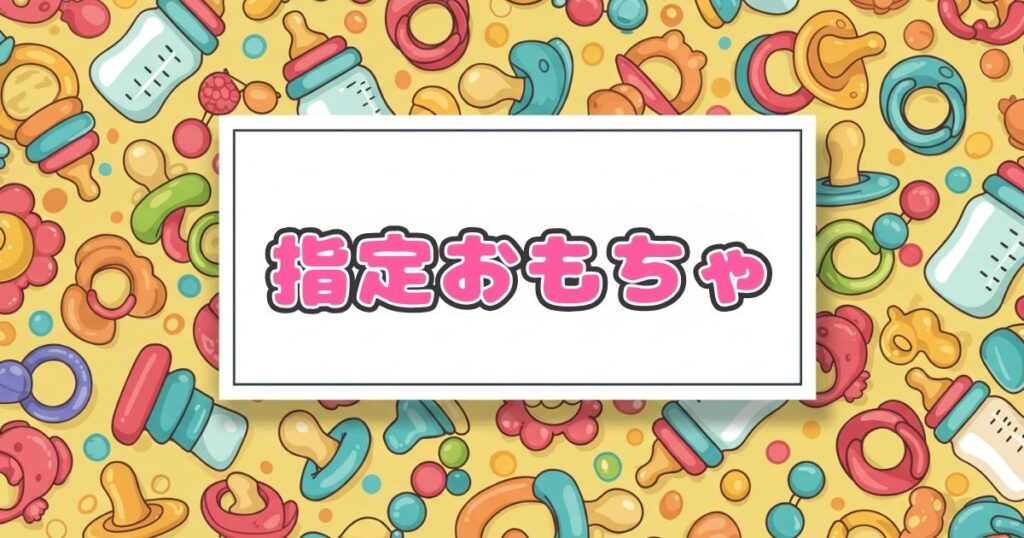
規制の対象となる「指定おもちゃ」にはいくつか種類があり、それぞれに特徴や輸入時の注意点があります。
ここでは代表的な例を取り上げ、輸入初心者でも理解しやすいようにポイントを整理して解説していきます。
事前にどのような玩具が規制の対象になるのかを知っておくことで、
余計なトラブルを回避でき、審査や届出もスムーズに進められるはずです。
正しい手続きを踏めば、安全性を確保しながら安心して輸入に取り組むことが可能になります。
出典:厚生労働省 → 指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて
乳幼児が口に触れることを前提としたおもちゃ
歯固めや哺乳びん型のおもちゃ、口に入れて遊ぶタイプのガラガラなど、
赤ちゃんが直接口に含むことを想定した製品は、食品衛生法の中でも特に厳格な規制対象となります。
乳幼児は大人に比べて体が未発達で、有害物質や化学物質に対する抵抗力が低いため、
こうした玩具には素材の安全性が強く求められます。
鉛やフタル酸エステルなどの有害成分が含まれていないかどうか、厳密な検査をクリアしている必要があります。
輸入者としては、製品を仕入れる前に必ず信頼できるメーカーの品質証明書や、
第三者検査機関による試験報告書を確認することが欠かせません。
証明書の有無や内容をしっかりチェックすることで、
後々のトラブルを未然に防ぎ、安全性の高い商品を消費者に届けることができます。
アクセサリータイプのおもちゃ
子ども向けのネックレスやブレスレット、指輪などのアクセサリー玩具は、
見た目のかわいらしさから人気がありますが、輸入にあたっては特に注意が必要なカテゴリーです。
こうした製品は小さなパーツが多数使われているため、
乳幼児や小さな子どもが誤って口に入れてしまい、
窒息や誤飲のリスクが発生する可能性があります。
さらに、使用される金属やプラスチックの素材によっては、
肌にかぶれやアレルギー反応を引き起こす恐れもあるため、対象年齢に応じた安全基準を理解し、
適合しているかを確認することが欠かせません。
輸入時には、装飾部分やチェーンの強度、パーツの大きさ・形状など
細かい部分まで品質をチェックする必要があります。
特に小さな部品が外れやすい製品は危険度が高いため、信頼できるサプライヤーから仕入れ、
事前に試験成績書や証明書を取り寄せて確認するのが安心です。
知育玩具
パズルや積み木、カードゲーム、ブロックなど、
遊びを通じて子どもの思考力や創造力を育む製品は「知育玩具」と呼ばれます。
単なる娯楽ではなく、学習要素を取り入れている点が大きな特徴です。
ただし、知育玩具の多くは小さなパーツを含むことがあり、
誤飲や窒息といったリスクを伴う場合があります。
そのため輸入の際には、食品衛生法に適合しているかどうかを確認することが重要です。
加えて、対象年齢に合った難易度や部品のサイズを選定することも欠かせません。
安全性をしっかり確保したうえで、知的発達や学習効果を意識した製品を選ぶことで、
子どもが安心して楽しめる理想的な玩具になります。
輸入者としては、信頼できるメーカーの証明書や検査機関の報告書をチェックし、
品質と安全性を両立させることが大切です。
食品衛生法の届出は不要!規制対象外となる乳幼児用おもちゃ
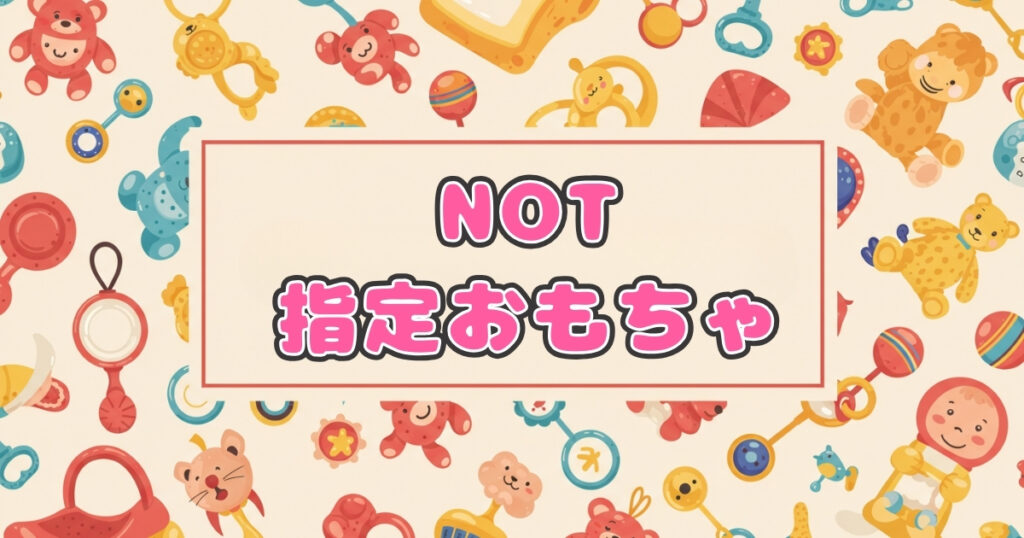
すべての乳幼児向け玩具が食品衛生法による届出の対象になるわけではありません。
実際には、口に入れることを前提としていない製品については、基本的に届出は不要とされています。
たとえば、赤ちゃんの視覚や聴覚を刺激するだけの布絵本や、触感を楽しむためのぬいぐるみ、ベビージムやベビーメリーなどは、
直接口に触れることを想定していないため、規制の対象外となるケースが多いです。
また、振ると音が鳴るラトル(ガラガラ)や、ベビーカーに吊り下げて使うタイプのおもちゃ、
カラフルなリングを連結するチェーン型トイなども、基本的には食品衛生法の届出を必要としない場合があります。
ただし注意すべきなのは、同じ布絵本であっても「歯固めのパーツが付属している」など、
一部に口に接触する可能性のある部品が含まれている場合は、届出が必要になるという点です。
このように製品の細かな仕様によって判断が分かれることがあるため、油断は禁物です。
輸入者としては、事前にサプライヤーへ
- 「口に触れるパーツがあるか」
- 「食品衛生法の対象になるか」
を確認し、そのうえで輸入手続きを進めると安心です。
さらに確実を期すなら、輸入前に厚生労働省の管轄機関へ直接問い合わせて確認しておくのがおすすめです。
届出が不要な製品を中心に取り扱えば、
余計なコストや手間を抑えつつ、よりスムーズに販売を開始できるでしょう。
指定おもちゃを中国から輸入するための流れ

中国から指定おもちゃを仕入れる際には、スムーズな取引を実現するために、
正しい手続きの流れを理解しておくことが不可欠です。
とくに、乳幼児が使用するおもちゃのように食品衛生法の規制対象となる「指定おもちゃ」を扱う場合、
通常の輸入よりも厳しい検査や書類手続きが求められる点に注意しなければなりません。
これらの規制は子どもの安全を守るために設けられているため、
輸入者としては必要な書類や検査の内容を事前に把握し、確実に準備を進めることが大切です。
以下では、輸入初心者でも理解しやすいように、
指定おもちゃを輸入する際の具体的な手順を解説していきます。
事前相談:製造工場・中国輸入代行業者との確認
最初のステップは、中国の製造工場や輸入代行業者から確認を取り、
仕入れ予定のおもちゃについて詳細な情報を集めることです。
素材の種類や対象年齢の設定、安全基準の適合状況などを確認し、
あわせて必要な検査証明書や試験成績書が用意されているかをチェックしておきましょう。
とくに、食品衛生法の対象となる「指定おもちゃ」を扱う場合は注意が必要です。
輸入をスムーズに進めるためには、厚生労働省や最寄りの検疫所に事前に相談し、
届出や検査に必要な書類をあらかじめ把握しておくことが安心につながります。
さらに、検疫所の担当者から直接アドバイスを受けておけば、
書類の不備による差し戻しや手続きの遅延といったトラブルを未然に防ぐことができます。
事前の段階でしっかり準備しておくことが、
輸入全体の流れをスムーズにする大切なポイントです。
出展:検疫所所在地一覧
輸入に必要な書類の準備
おもちゃを中国から輸入する際には、まず基本的な貿易関連の書類を整えておく必要があります。
代表的なものとしては以下のものが挙げられます。
- 商品の明細を記載したインボイス(商業送り状)
- 梱包内容を示すパッキングリスト
- 貨物の引き渡しに関する証明書であるB/L(船荷証券)
これらは輸入の際に必須となる基本書類です。
加えて、対象となる製品が食品衛生法の規制を受ける場合には、
検査証明書や試験成績書といった追加書類の準備が求められることがあります。
これらの書類は製品の安全性を裏付けるものであり、
届出や検査をスムーズに進めるために欠かせません。
輸入者としては、事前に必要な書類の一覧を整理し、
工場や代行業者に早めに依頼して準備しておくことが重要です。
あらかじめチェックを済ませておけば、
書類の不足や不備によって手続きが止まるリスクを防ぎ、輸入を滞りなく進められるでしょう。
検疫所への届出
食品衛生法の規制対象となるおもちゃを輸入する場合には、
検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出することが必須です。
この届出がなければ、日本国内において正式に輸入手続きを進めることはできません。
提出された書類は検疫所で審査され、内容に問題がなければ輸入が許可されます。
しかし、もし不備があったり追加で確認が必要な事項が見つかった場合には、検疫所から連絡が入ります。
その際はできるだけ早く対応しなければ、輸入のスケジュール全体に影響が出る可能性があります。
また、届出のタイミングも重要です。
中国から商品が発送される前に届出を済ませておくのが理想的です。
日本の税関で届出が未提出だと、その場で貨物が止められてしまい、
余計な保管料や手続きの遅延につながりかねません。
事前の届出は輸入をスムーズに進めるための必須ポイントと言えるでしょう。
出展:食品等輸入届出フォーム
出展:届出書類の書き方
検査の実施
食品衛生法の対象となるおもちゃは、
検疫所や指定検査機関、あるいは輸入者自身が手配する検査によって、
有害物質の有無や安全基準への適合性を確認します。
ここでの検査は単なる形式的なものではなく、
消費者の安全を守るために非常に重要なステップです。
具体的には、使用されている素材や塗料に鉛やフタル酸エステルなどの有害成分が含まれていないか、
小さな部品が誤飲や窒息のリスクを伴わないかなど、細部まで厳しくチェックされます。
もし検査の結果、基準を満たしていない部分が見つかった場合には、
追加の改善措置や再検査が必要となり、その分コストや時間がかかる可能性があります。
輸入を円滑に進めるためには、事前に製造工場へ品質管理の徹底を依頼し、
検査をクリアできる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
食品等輸入届出済証の発行
検査を無事にクリアすると、検疫所から「食品等輸入届出済証」が発行されます。
この書類は、輸入したおもちゃが食品衛生法に定められた安全基準を満たしていることを
公式に証明する重要なものです。
届出済証を取得することで、
輸入者ははじめて日本国内での販売や流通を正規に行うことができます。
逆に、この書類がなければ、商品を市場に出すことは認められず、
税関で差し止められたり販売停止を命じられる可能性があります。
つまり、食品等輸入届出済証は単なる形式的な書類ではなく、
日本で安全におもちゃを販売するための「通行証」とも言える存在です。
輸入者にとっては最終的に必ず手に入れるべき重要書類であり、
取得できれば安心して事業を展開できるようになります。
通関手続き:日本側
最終段階として、日本の税関に対して正式に輸入申告を行います。
この際には、関税や消費税といった必要な税金を支払うことで、通関審査が開始されます。
提出した書類や申告内容に問題がなければ、税関から通関許可が下り、
輸入したおもちゃを国内で販売・流通させることが可能になります。
ただし、申告書類の不備や記載ミスがあると、追加の確認や修正を求められ、
場合によっては余計な保管料や時間的ロスが発生する恐れがあるため注意が必要です。
すべての届出・検査・税関手続きを正しく完了させることで、
ようやく中国から輸入したおもちゃを日本市場に流通させることができます。
輸入のゴールはここにあり、同時に安全性を担保した商品を届けるための
大切なプロセスであることを意識しておくと良いでしょう。
関税について詳しくまとめた記事は以下になります。

関税の基礎知識まとめ|個人輸入から中国輸入ビジネスまで役立つ完全ガイド
指定おもちゃか迷ったら、無料の事前相談を活用しよう
中国からおもちゃを輸入する際には、
「この製品は指定おもちゃにあたるのか?」と判断に迷うケースは少なくありません。
指定おもちゃとは、食品衛生法やST基準などの日本独自の安全基準に適合しなければ販売できない子ども向け玩具を指します。
もし規制に違反して販売を行えば、販売停止処分だけでなく罰則を受けるリスクもあり、
初心者にとっては非常に大きな不安要素となります。
こうしたリスクを避けるために活用したいのが、
製品評価技術基盤機構(NITE)や専門の輸入代行業者が提供している無料の事前相談サービスです。
これらを利用することで、輸入前の段階で「届出や検査が必要かどうか」を確認することができます。
さらに、日本各地の検疫所でも輸入者をサポートする体制が整っています。
検疫所では「このおもちゃは食品衛生法の対象になるのか?」といった疑問に答えてくれる事前相談を受け付けており、
公式サイトでは安全基準や必要な手続きに関する情報も公開されています。
多くの場合これらのサービスは無料で利用可能で、初心者にとって大きな安心材料になるでしょう。
場合によっては、商品画像や仕様書を送るだけで対象かどうかを確認してもらえるケースもあります。
輸入に不安を感じたときは、自己判断で進めるのではなく、
まずは専門機関に相談して安全を確保することが成功への近道です。
電気用品安全法と電波法にも注意が必要
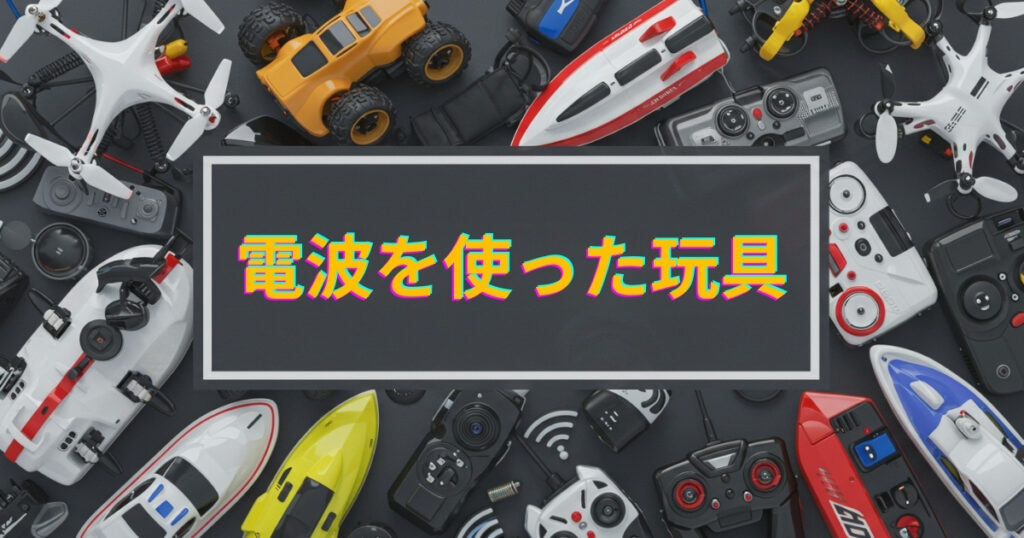
中国からおもちゃを輸入する際には、食品衛生法だけでなく、
電気用品安全法や電波法といった他の法律が関わるケースもあるため注意が必要です。
まず、電気用品安全法は家庭用電気製品の安全を確保するために制定された法律であり、
コンセントを使用するタイプのおもちゃや電源を必要とする製品はこの規制の対象となります。
該当する商品は、国内販売にあたりPSEマークの取得が義務付けられているため、
仕入れ前に製造工場から発行される証明書類や検査成績を必ず確認しておく必要があります。
PSEマークについては下記の記事を参考にして下さい。
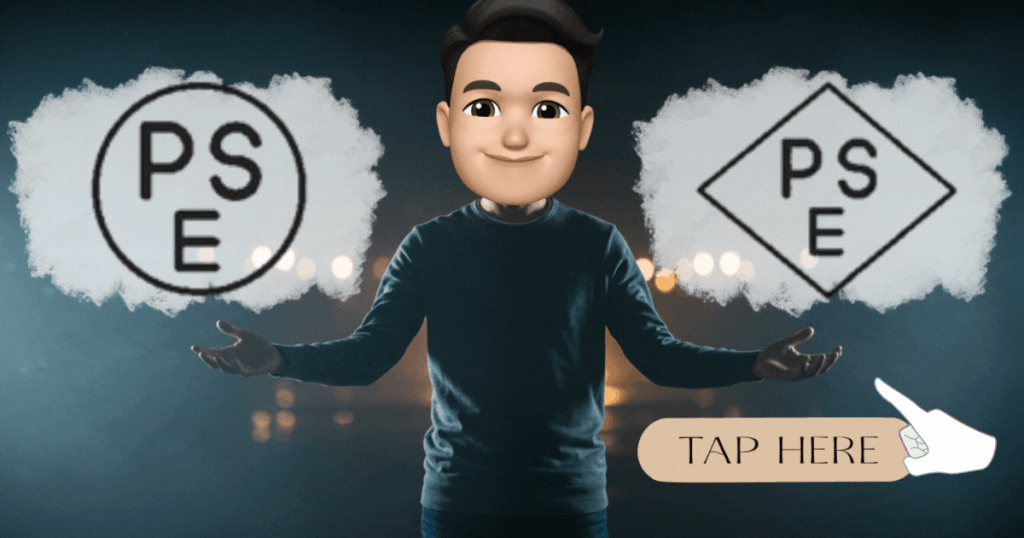
中国輸入でコンセント系を仕入れるなら必読!PSEマーク取得方法の全手順と偽物を見分けるポイント
一方で、電波法は無線通信機能を持つ製品を規制しています。
リモコン操作で動くラジコンカーやドローン、Bluetooth機能を搭載したおもちゃなどは、
出荷前に技適マーク(技術基準適合証明)を取得しなければなりません。
技適マークのない製品は、国内での使用や販売が禁止されるだけでなく、
輸入段階で差し止められる可能性もあります。
特に子ども向けのおもちゃは安全基準が厳格に設定されているため、
対象商品ごとに電源の有無・通信機能の有無・使用目的を正確に把握することが大切です。
これらを事前に確認しておくことで、
輸入後のトラブルや販売停止といったリスクを避けられるでしょう。
まとめ

中国からおもちゃを輸入する際には、価格やデザインといった魅力に目を奪われがちですが、
最も重要なのは法規制を正しく理解し、安全性を確保することです。
特に乳幼児向けのおもちゃは、食品衛生法の規制対象となるケースが多く、
事前相談・書類準備・検査・届出といったプロセスをきちんと踏むことが不可欠です。
さらに、電気用品安全法によるPSEマークの取得や、
電波法に基づく技適マークの確認が必要な場合もあり、
該当する商品を扱う際には十分な注意が求められます。
一見すると手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、
事前に必要な規制や書類を把握して準備しておけば、輸入をスムーズに進められます。
また、検疫所やNITEが提供している無料の相談窓口を活用すれば、
初心者でも安心して一歩を踏み出せるでしょう。
安全性を確保したうえで輸入を行うことは、消費者からの信頼を得ることにも直結します。
確実な手続きと正しい知識を身につけ、リスクを回避しながら、
中国輸入ビジネスを長期的に安定して発展させていきましょう。