
こんにちは。
中国輸入OEMマスター龍です😀
今回はPSEマークについて解説していきます
中国から電化製品を仕入れようと思ってますが、
PSEマークって何ですか??

これは、国ごとに電圧や安全基準が異なるため、
そのままでは発火や感電といった事故につながる恐れがあるからです。
PSEマークとは
「Product Safety Electrical appliance & materials」の略で、
対象となる電気用品が電気用品安全法で定めた安全基準を満たしていることを示すマークです。
2001年に施行された電気用品安全法により、
テレビや冷蔵庫などに5年の猶予期間を経て全面的に導入され、
現在では国内外で製造・輸入される電気用品に広く適用されています。
電気用品の事故を防ぎ、消費者の安全を守るために作られた制度であり、
海外から家電を仕入れて日本で販売する場合も例外ではありません。

実際、アリババでも「PSEマーク付き」
と表示された家電を目にすることがありますが、注意が必要です。
というのも、PSEマークを適切に表示する責任は輸入者側にあり、
単にマークが付いているだけでは法的に有効とは限りません。
特に、マークの近くに輸入事業者名が併記されていない製品は、
偽造PSEの可能性が高く、法的リスクを伴うため十分な確認が不可欠です。
PSEマークは日本で電気製品を安全に販売するための“合格証”のような存在です。
一見するとハードルが高そうに感じるかもしれませんが、
実際には決められた流れに沿って進めていけば意外とシンプルに手続きが可能です。
本記事では、必要な基礎知識から具体的な付ける手順、
さらに偽物を見抜くための注意点まで、わかりやすく順を追って解説していきます。
PSE認証について
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、
電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、
電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
電気用品安全法 → 第一章総則第一条
中国から家電を仕入れる際に必ずといっていいほど耳にするのが 「PSE認証」 です。
日本国内で電気製品を正規に販売するためには、このマークが表示されていなければならず、
いわば流通の“入場券”のような存在といえます。
しかし、これから輸入ビジネスを始めようとする方にとっては、
- 「そもそもPSEって何を意味するの?」
- 「自分が扱いたい商品は対象になるの?」
- 「どうやって本物かどうか確認すればいいの?」
といった疑問が湧いてくるはずです。
そこで本記事では、PSE認証の基本的な仕組みから、
マークの種類、確認方法までを体系的に整理してお伝えします。
コンテンツ
電気用品安全法とPSEマークの概要

PSEマークはなぜ必要?
電気用品安全法は、電気製品による
火災や感電といった危険を防止することを目的とした法律です。
製造事業者や輸入業者は定められた手続きを履行した上で、
製品にPSEマークを表示しなければなりません。
この制度により、日本の電圧・周波数に適合しない危険な電気用品や、
粗悪な製品が市場に出回ることを防いでいます。
PSEマークは政府から許可を受ける免許ではなく、
「法定の義務を果たしたことを示す自己表示」である点が特徴です。
輸入業者が自らの責任で適合確認を行い、
その記録を保管したうえでマークを表示します。
つまり、輸入者が責任を負う形で安全性を証明する仕組みであり、
輸入者の表示がなければ販売・輸入は認められません。
対象となる製品と対象外の製品
電気用品安全法はすべての電気製品を対象としているわけではありません。
法律で指定された116品目の「特定電気用品」と、
その他341品目の「特定電気用品以外」の電気用品が対象で、いずれもPSEマークが必要です。
一方、以下のような製品はPSE対象外とされています。
| PSE対象外の例 | 理由・補足 |
|---|---|
| リチウムイオン蓄電池 | 単体の蓄電池は対象外だが、モバイルバッテリーなど製品として販売する場合はPSE対象になることがある |
| 電線類・蛍光灯電線 | 工事材料に相当し、PSEの規制対象外 |
| フロアダクト | 床用配線器具 |
| 温度ヒューズ・光電式自動点滅器 | 安全装置や制御装置に分類される |
| ミシン用コントローラー | 専用品のため対象外 |

USBで使用出来る製品は対象外なので、
PSEマークは不要です。
ですが、USBで使用するモバイルバッテリーは対象外です。
特定電気用品や特定電気用品以外の対象品目に該当するかは、
経済産業省の一覧表で確認する必要があります。
また、2019年2月以降はモバイルバッテリー(ポータブルリチウムイオン蓄電池)も
事故増加を受けてPSEマークが義務化されました。
安全基準に適合しないモバイルバッテリーの販売は禁止され、
違反品は出品停止などの措置が取られることが経済産業省から公表されています。
PSEマークの種類と違い
PSEマークには二つの形状があります。
いずれも電気用品安全法の基準に適合したことを示すマークですが、対象となる品目や検査方法が異なります。
| 詳細 | 形状:丸 | 形状:ひし形 |
|---|---|---|
| PSCマーク(消費生活用製品安全法) | 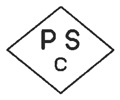 | |
| PSEマーク(電気用品安全法) |  |  |
| PSLPGマーク(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律) |  | |
| PSTGマーク(ガス事業法) |  |  |
菱形PSEマーク(特定電気用品)

菱形のPSEマークは、116品目の「特定電気用品」に付けられるマークです。
これらは以下のように特に危険性が高い製品です。
- 長時間無監視で使用されるもの
- 人体に直接触れるもの
- 社会的弱者が使用するもの
具体的な例としては以下が該当します。
- 電気温水器
- 自動販売機
- 直流電源装置
- 電熱式・電動式のおもちゃ
菱形マークの製品は、政府が認めた登録検査機関での試験に合格し、
工場監査(生産設備や品質管理体制の確認)を受ける必要があります。
表示する際は登録検査機関名も併記しなければならず、第三者認証が必須です。
丸形PSEマーク(特定電気用品以外)

丸形のPSEマークは、
特定電気用品以外の341品目に付けられるマークです。
- 電気こたつ
- テレビ受信機
- 電気スタンド
- 電気冷蔵庫
上記のような一般的な家庭用電気製品が該当し、
リチウムイオン蓄電池を含む場合もあります。
丸形マークの場合、第三者機関による検査は任意で、
自主検査に基づいて表示することが多いです。
ただし、製造者名や定格電圧・消費電力などを併記するのが一般的で、
輸入業者は検査記録を少なくとも3年間保管しなければなりません。
Sマークとの違い
PSEマークに似た「Sマーク」は、
電気製品認証協議会(SCEA)が
第三者の立場で電気用品の安全性を確認・認証した証です。
法律上の義務はありませんが、
PSEマークとSマークの両方が付いている製品は、
製造者や輸入業者が第三者認証も受けたことを意味し、安全性への信頼が高まります。
製品選びの際は両マークが表示されているかもチェックすると良いでしょう。
PSEマークの基本まとめ
PSEマークは、日本の 「電気用品安全法」 に基づき、
安全性が確認された電気製品に付けられる認証マークです。
形には 丸型とひし形 があり、対象製品によって使い分けられます。
| 形状 | 詳細 |
|---|---|
 | 通称「丸PSE」 一般的な電気用品に表示。 メーカーや輸入者が自主検査を行い、 安全性を確認した製品に付されます。 |
 | 通称「角PSE」 電源コードやACアダプターなど、 特にリスクが高い「特定電気用品」に表示。 登録検査機関による適合性検査が必須です。 |
このマークがなければ日本国内で販売することは法律で禁止されており、違反すれば罰則もあります。
また、確認・表示の責任は輸入者自身にある 点も忘れてはいけません。
個人やスタートアップ企業で家電製品を販売する場合、丸PSE扱いの製品になることが多いです。
角PSEの認証を受ける為には、高額な検査費用が必要になる為です。
特定電気用品「角PSEは産業用パーツや部品系が多く、特定電気用品以外の電気用品「丸PSE」は日用家電が多いです。
出典:特定電気用品(116品目)一覧
出典:特定電気用品以外の電気用品(341品目)一覧
PSE認証が必要な理由
電気製品は便利な反面、火災や感電といった事故のリスク を伴います。
そのため日本では「電気用品安全法」によって、
一定の安全基準を満たしていることを示す PSEマーク の表示が義務付けられています。
このマークがなければ、日本国内での販売は違法となり、罰則を受ける可能性もあります。
海外で人気の商品であっても、PSE認証がなければ日本では流通できません。
したがって、輸入前にPSEマークの有無を必ず確認することが必須 です。
これは形式的な規則ではなく、消費者の安全を守るための重要なルールなのです。
PSE認証の確認方法
輸入予定の商品がPSE認証を受けているかどうかは、
商品本体やパッケージにPSEマークが表示されているか を確認するのが基本です。
信頼できる業者であれば、商品ページにも「PSE取得済み」と明記しているケースが多いでしょう。
一方、マークの記載や写真が見当たらない場合は注意が必要です。
少しでも不安があるときは、仕入れ前に販売者やメーカーへ認証証明書の提示を求めることが必須 です。
証明書を出せない業者はリスクが高いため、取引は避けるのが安全です。
偽物のPSEマークに注意
中国から輸入される製品の中には、偽造されたPSEマーク が付いている例もあります。
見た目だけでは判断できないため注意が必要です。
本物であれば、認証機関や経産省のデータベースで登録状況を確認可能 です。
マークの有無だけで安心せず、証明書や型番の一致 まで確認することが大切です。
安さにつられて偽物を仕入れてしまうと、販売停止や罰則のリスク に直結します。
初心者こそ慎重にチェックする習慣をつけましょう。
PSEマークは事業者が自主的に表示するもの
PSEマークは製造者や輸入事業者が責任を持って表示するもので、
取得するものではありません。
また、個人が勝手につけられるものではありません。
PSEマークを表示するのは輸入事業者
日本で販売される電気製品のPSEマークは、海外メーカーではなく日本の輸入事業者が表示責任を負います。
輸入者は「自ら安全性を確認した証」として、会社名や住所とともにマークを付けなければなりません。
つまり、中国から仕入れてそのまま販売するだけでは、電気用品安全法に違反する可能性 があります。
輸入者は単なる購入者ではなく、安全を担う事業者としての自覚が求められるのです。
メーカー表示だけでは不十分
中国の工場やメーカーがあらかじめ PSEマークを印字している製品 を目にすることがあります。
しかし、それだけでは日本国内で正規に販売する条件を満たしているとは言えません。
理由は明確で、日本の法律では 輸入した事業者が最終的な責任を負う と定められているからです。
仮に事故や不具合が発生した場合、責任を追及されるのはメーカーではなく、日本で販売した輸入事業者となります。
つまり、「海外メーカーが表示しているから大丈夫」と安易に信じるのは危険です。
必ず 自分自身が表示主体である という意識を持ち、責任ある立場でPSEマークを取り扱う必要があります。
表示を怠るリスク
PSEマークを正しく表示しないまま電気製品を販売すると、
電気用品安全法違反 となり、罰則を受ける可能性があります。
罰金や販売停止措置だけでなく、最悪の場合は在庫の回収や廃棄を求められるケースもあります。
さらに一度違反が発覚すると、消費者や取引先からの信用を大きく損ない、
今後のビジネス全体に深刻な影響を及ぼしかねません。
特にネットショップでは、購入者からのレビューや通報によって問題がすぐに表面化しやすく、リスクは想像以上に高いのです。
だからこそ、初心者のうちから 「PSE表示は輸入事業者の責任」 という意識を徹底し、
確実に表示を行う習慣を身につけることが不可欠です。
PSEマークの届出から認証、輸入まで

中国から家電製品を輸入して日本で販売するには、
PSEマークを取得するための一定の手続き を踏む必要があります。
単に仕入れて販売するだけではなく、
輸入事業者として「この製品は日本の安全基準を満たしている」
と証明できるプロセスをきちんと経ることが求められます。
この流れを無視すると違法販売につながるリスクがあるため、
事業者は「買う側」ではなく「安全を保証する責任者」という立場を自覚することが重要です。
そこで本記事では、初心者の方でも迷わず理解できるように、
届出から検査、認証取得、そして実際の輸入に至るまでの一連のステップ を順を追ってお伝えします。
① 事業開始届の提出
電気用品の輸入・製造を開始した日から30日以内に、経済産業省へ事業開始届を提出します。
これにより輸入事業者として登録されます。
この手続きは「これからこの製品を日本国内で取り扱います」と
国に正式に通知するための重要なプロセス です。
届出を行わなければ、その後の認証や販売につなげることはできません。
もちろん、実店舗での販売に限らず、
ネットショップやECサイトでの販売を予定している場合も例外ではなく、
必ず事前に届出を済ませておく必要があります。
届出は、個人事業主でも法人でも事業者なら可能です。
いわば、ここでの届出がPSEマーク取得と輸入の 第一歩=スタートライン となります。
② 自主検査と記録の保管
輸入業者はロットごとに自主検査を実施し、結果を3年間以上保管しなければなりません。
自主検査記録には試験日、検査項目、測定結果、担当者名などを記録します。
この確認作業は、必ずしも大規模な試験機関での検査に限られるものではありません。
場合によっては、チェックリストを活用した基本的な安全性の確認 も含まれます。
大切なのは「製品を安心して販売できるか」を事業者自身が見極める姿勢です。
初心者にとっては専門的に感じられるかもしれませんが、
必要であれば代行業者へ依頼する方法 もあります。
こうした外部の力を活用すれば、手続きのハードルは大きく下がります。
安全確認は、輸入ビジネスを継続的に行う上で欠かせない基盤となる作業です。
③ 適合性検査
ひし形PSEマークの場合は、登録された検査機関で「適合性検査」を受けます。
検査機関では、安全性を詳細に調べ、基準を満たしているかどうかを確認します。
基準を満たしていれば正式に認証が与えられ、ひし形PSEマークを製品に表示できます。
このプロセスには一定の時間と費用がかかります。
しかし、それは単なるコストではなく、消費者に安全を保証するための不可欠な投資 と考えるべきです。
なお、適合証明証の発行にかかる審査期間や流れの詳細については、
代行業者や認証サポート会社に相談するのが効率的 です。
④ PSEマークの表示:貼付 or 印字
検査に合格した後は、輸入事業者自身の責任でPSEマークを表示します。
表示方法には、製品本体やパッケージへ直接印字する方法のほか、
専用のステッカーを貼り付ける方法もあります。
ここで重要なのは、単にマークを付けるだけでは不十分だという点です。
輸入事業者の名称や住所を併記することが必須 であり、
これによって初めて「この製品の安全性を日本の基準に満たしている」事が明確になります。
表示を怠ったり不完全なまま販売した場合には、
法律違反として罰則や販売停止の対象 となるため、
細部まで確実に対応することが求められます。
出典:経済産業省 → 製品安全に関する諸制度 → 事業者の義務 → 表示の方法
⑤ 輸入手続きへ
最終段階として、認証を取得した状態で正式な輸入手続きを進める ことになります。
税関ではPSE関連の書類を提示するよう求められる場合があるため、
証明書や届出の控えは必ず手元に準備しておくことが重要です。
輸入が完了した後も気を抜いてはいけません。販売開始前には再度製品を点検し、
認証内容と実物が一致しているか、表示に不備がないか を確認しておく必要があります。
PSE認証を取得したからといってそこで終わりではなく、
輸入事業者には継続的に製品の安全性を管理する責任があります。
こうした取り組みを徹底することで、
結果的に 長期的に信頼されるショップ運営やブランド力の向上 につながります。
義務付けられているPSマークの例

USBタイプの製品ならPSEマークは不要になります。

USBで電源を取れる製品も沢山ありますので、
USB製品がオススメですよ。
PSE認証の検査機関

PSE認証は、日本で電気製品を販売するために欠かせない、法的にも非常に重要な認証制度 です。
この制度は、電気用品が定められた安全基準に適合していることを確認し、
最終的には消費者の安心と信頼を守ることを目的としています。
ただし、PSE認証を取得するためには、単に申請するだけでは済みません。
専門の検査機関での安全性試験や、詳細な技術資料・必要書類の準備 が必須となります。
これらを疎かにすると認証は下りず、結果的に日本国内での販売が不可能になります。
そこでPSE認証を取得するための主要な検査機関をご紹介します。
それぞれの特徴や選び方のポイントについて解説致します。
TÜV Rheinland Japan(テュフ ラインランド ジャパン)
本社をドイツに置く TÜV Rheinland(テュフ ラインランド) は、
世界的に高い信頼を得ている国際的な試験・認証機関です。
グローバルに展開しており、日本国内にも複数の拠点を持ち、国内事業者が利用しやすい体制を整えています。
同社はPSE認証をはじめとする電気製品の安全性評価を幅広く手がけており、
さらに環境試験、品質試験など、電気分野以外の試験サービスにも対応しているのが特徴です。
Intertek Japan(インターテック ジャパン)
Intertek(インターテック) は、英国に本社を構える国際的な試験・認証機関で、
PSE認証を取得するための試験サービスを提供しています。
グローバルに拠点を持ち、日本国内からでもスムーズに依頼できる体制が整っています。
同社の大きな特徴は、対応スピードの早さとコストパフォーマンスの高さ にあり、
多くの企業から信頼を得ています。
特に輸入ビジネスを始めたばかりの事業者や、初めてPSE認証に取り組む企業に対しても、
分かりやすいサポートが充実している点は大きな魅力です。
UL Japan(ユーエル ジャパン)
UL(Underwriters Laboratories) は、アメリカに本拠地を置く世界的に有名な認証機関で、
日本国内でもPSE認証サービスを提供しています。
高い実績を持ち、製品の安全規格に精通している点が大きな強みです。
ULの最大の特徴は、製品の安全性や規格への適合性を厳格な基準で評価する基準 にあります。
グローバル市場への販売展開を視野に入れている企業にとってはULの認証取得は大きなメリット となります。
輸入ビジネスを日本国内にとどめず、海外展開を考える事業者にとって心強い選択肢と言えるでしょう。
日本電気安全環境研究所(JET)
JETは、日本国内でPSE認証の試験を実施している代表的な公的機関です。
国内の法規や技術基準に則した試験を提供しており、PSE認証を取得する企業や中小企業にとって、
安心して利用できる信頼性の高い選択肢として広く認知されています。
JETを活用する最大のメリットは、国内市場での製品信頼性や取引先からの信用を獲得しやすくなり、
ビジネスの安定した展開につながります。
SGS Japan(エスジーエス ジャパン)
SGS は、スイスに本社を構える認証機関のひとつであり、
PSE認証をはじめとした幅広い試験・認証サービスを提供しています。
同社の大きな特徴は、国際規格への幅広い対応と効率的な試験プロセス にあります。
その為、多くの企業から信頼されています。
PSE認証にかかる費用は?
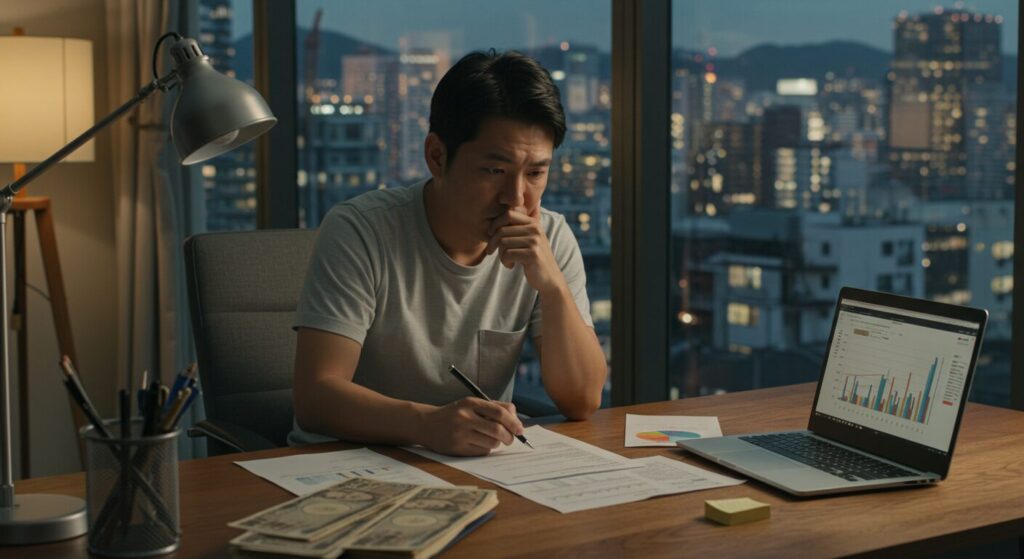
PSE認証を取得するためには、さまざまな工程ごとに費用が発生 します。
必要なのは検査機関での試験費用だけではありません。
認証に先立つ届出の手続きや、申請書類の作成にもコストがかかります。
特に初めて取り組む事業者にとっては
「どこにどれくらいの費用がかかるのか」が見えにくい部分でもあります。
そこで、初心者でもイメージしやすいように、各費用 を解説していきます。
認証試験費用
製品の安全性を確認するための試験には、おおよそ数万円から数十万円規模の費用 が発生します。
金額は一律ではなく、製品の種類や検査内容の複雑さによって大きく変動します。
たとえば、シンプルな構造のACアダプター類であれば比較的安価に収まるケースもあります。
しかし、複雑な電子機器では必然的に高額になりやすいのが実情です。
さらに、どの検査機関を利用するかによっても料金体系が異なるため、
複数の機関から事前に見積もりを取って比較することが不可欠 です。
特に初心者の場合、この費用感に驚くことが多いため、
事前にしっかり予算を把握しておくことが安心につながります。
登録費用
特定電気用品を扱う場合には、登録検査機関での手続きと登録費用 が必須となります。
一般的には数万円程度の負担が発生することが多く、コストとして避けられない部分です。
さらに注意すべきなのは、この登録は一度で終わりではなく、
一定期間ごとに更新が必要となるケースもある という点です。
更新を怠ると販売資格を失い、結果的に商品を取り扱えなくなるリスクもあります。
確かに費用は決して安くはありませんが、
日本で合法的に電気製品を販売するためには欠かせないステップです。
固定的なコスト として資金計画に反映させておくことが安心につながります。
書類作成の費用
PSE認証を取得する際には 必要な書類の準備 にもコストが発生することがあります。
自分で作成すれば印刷代や事務的な費用程度で済むため比較的安く抑えられますが、
専門家や代行業者に依頼した場合は数万円規模の費用がかかるのが一般的です。
特に初心者に多いのが、書類の不備によって手続きが中断してしまうケースです。
記載内容のミスや不足があれば、その都度修正対応が必要となり、
結果的に時間とコストのロスにつながります。
そのため、確実に進めたい場合は外部の専門家に依頼する選択肢 が検討されることも少なくありません。
結局のところ、費用を節約するか、それとも安全性とスピードを優先するかのバランスが重要です。
書類は単なる形式的なものではなく、認証手続き全体を左右する重要な要素 であることを忘れてはいけません。
代行業者の費用
PSE認証の取得を専門業者に依頼する場合は、サービス利用料が別途発生します。
料金は依頼内容やサポート範囲の広さによって変動し、
おおよその目安としては数万円から十数万円程度が一般的です。
代行業者を利用すると、検査の手配から必要書類の作成までを一括で任せられるため、
自分で手続きを進める際に発生しがちな手間や不安を大幅に軽減できます。
特に初めてPSE認証を取得する人にとっては、
専門知識がなくてもスムーズに進められる点が大きなメリットといえます。
ただし、その分コストが上乗せされるのは事実です。
費用をかける以上は、経験や実績がしっかりしており、
安心して任せられる信頼性の高い業者を選ぶことが重要になります。
各費用の合計(目安)
PSE認証の取得にかかる総費用は、すべてを合計すると一般的に数十万円規模になることが多いです。
製品がシンプルな構造であれば10万円台で収まるケースもありますが、
複雑な製品では50万円を超えることも珍しくありません。
初心者にとって、この金額は決して小さな負担ではなく、最初は高額に感じるでしょう。
ですが、PSE認証は製品の安全性を公的に証明するために欠かせないプロセスであり、
将来的なトラブルを防ぐための必要な投資といえます。
そのため、事前にしっかりと予算計画を立て、
段階的に進めることが費用を無駄にしないための重要なポイントとなります。
PSE認証取得までの期間(目安)
PSE認証は申し込んだその日からすぐに取得できるものではなく、
複数の工程を順を追って進める必要があります。
実際には、製品の試験、必要書類の準備、そして審査といったプロセスを一つずつクリアしていくため、
どうしても一定の時間がかかります。
そのため、全体の流れや各工程にかかる期間を事前に把握しておくことが、計画的に進めるうえで非常に重要です。
ここでは、各ステップごとの目安期間を解説していきます。
PSE認証取得までの期間についての内訳
PSE認証の取得プロセスは、
大きく分けて「試験」「書類の準備」「審査」「マーク発行」という4つのステップで構成されています。
これらはそれぞれが独立した工程であり、必ず順番に進めていく必要があります。
また、どのステップも数日で完了するものではなく、ある程度の期間を見込んでおかなければなりません。
特に、製品の種類や検査機関のスケジュール状況によって所要時間が前後する点には注意が必要です。
そのため、まずは全体の流れをしっかり把握し、
あらかじめおおよそのスケジュールを立てておくことが、スムーズな認証取得につながります。
試験にかかる期間(目安)
製品の安全試験には、一般的に早くても2〜4週間程度の期間が必要です。
シンプルな構造の電気製品であれば比較的短期間で完了することもありますが、
複雑な製品の場合は、試験だけで数か月かかるケースも珍しくありません。
さらに、検査機関の予約状況や繁忙期によっては、
試験の開始までに想定外の待ち時間が発生することもあります。
そのため、全体のスケジュールには必ず余裕を持たせ、
輸入前の段階で検査機関のスケジュールや混雑状況を事前に確認しておくことが安心につながります。
書類準備にかかる期間(目安)
PSE認証に必要な届出書類や試験関連の書類を一通りそろえるには、
一般的に1〜2週間程度が目安とされています。
自分でゼロから準備する場合は、情報収集や書式の確認に時間がかかり、
想定以上に日数を要することも珍しくありません。
さらに、提出した書類に不備が見つかれば、その修正対応でスケジュールが後ろ倒しになる可能性があります。
特に初心者の場合は、専門知識が不足している分、
外部のサポートや代行サービスを利用することで全体の準備期間を短縮できるケースもあります。
無駄な遅延を避けるためには、できるだけ早い段階で書類作成に着手し、計画的に進めることが重要です。
認証機関での審査期間(目安)
試験と必要書類の準備が完了すると、次は認証機関による正式な審査の段階に進みます。
通常、この審査には約2〜4週間ほどかかるのが一般的です。
ただし、提出する書類の量や検査機関の混雑状況によって、所要期間が前後することがあります。
また、もし書類に不備が見つかれば差し戻しとなり、修正対応のために追加の日数が必要になります。
こうした遅延を防ぐためには、申請前の段階でしっかりと書類を確認し、
抜け漏れがないよう丁寧にチェックしておくことが、スムーズな審査通過のカギとなります。
PSE認証マーク発行までの期間(目安)
審査を無事にクリアすると、次はいよいよPSEマークを発行する段階に進みます。
この工程自体はそれほど長い時間を要しませんが、
実際にはマークの印字の準備や、表示内容の準備に数日から1週間程度かかるのが一般的です。
また、PSEマークは製品本体やパッケージに正しく表示する必要があるため、
輸入者の名称や住所を含めた表示データを事前にしっかりと用意しておくことが重要です。
こうした準備が整い、製品や梱包に正確に反映されてはじめて、正式に販売を開始することができます。
全ての期間の目安
全体の流れを踏まえると、PSE認証の取得には通常約2〜3か月ほどの期間が必要とされています。
製品の構造がシンプルで、かつ書類の準備や検査が滞りなく進めば、1か月程度で完了するケースもあります。
しかし、製品の仕様が複雑だったり、書類に不備が多かったりすると、
手続きの差し戻しや追加試験が発生し、最終的には半年近くかかることも珍しくありません。
初心者の多くが「想定より時間がかかる」と感じるのはこのためです。
そのため、できるだけ早い段階から準備を進め、余裕を持ったスケジュールを立てておくことが、
スムーズにPSE認証を取得するための重要なポイントとなります。
PSEマークを表示しなかった場合の罰則規定について
電気用品安全法では、PSEマークの表示義務に違反した場合の罰則規定が明確に定められています。
具体的には、PSEマークが付いていない電気用品を販売したり、販売目的で店頭やネット上に陳列したりすると、
法人・個人のそれぞれに対して以下のような罰則が適用される可能性があります。
| 法律 | 詳細 | 罰則 |
|---|---|---|
| 電気用品安全法第57条 |
| 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科。 |
| 電気用品安全法第58条 |
| 30万円以下の罰金。 |
| 電気用品安全法第59条 | 法人の代表者、法人、代理人、使用人その他の従業員が、その法人の業務に関して違反行為を行った場合は、法人に対して罰金刑が課せられます。 | 第57条第58条に準じる。 |
| 電気用品安全法第60条 |
| 20万円以下の罰金。 |
PSEマークについての受け付け窓口
PSEマークの届出手続きや、製品が丸型PSEと角型PSEのどちらに該当するのかなど、
判断に迷う点がある場合は、経済産業省に直接確認するのが最も確実です。
代行業者に相談する場合は、たとえば
- 「中国のCE認証が取得できるか」
- 「中国品質認証センター(CQC)を通じて適合性検査を依頼できるか」
といった内容であれば、対応してもらえるケースが多いです。
ただし、PSEマークの制度全般や法的な要件については、
日本国内の所轄官庁である経済産業省に問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。
偽物のPSEマークについて

PSEマークの表示義務は日本の法律で定められているため、
タオバオやアリババなど中国のECサイトでPSEマーク付きの製品を見かけた場合は、まず偽物を疑った方が良いです。
まれに、工場の事情で正規のPSEマークが表示されているケースもありますが、
特に初心者の方はリスクを避けるためにも、こうした製品を安易に扱わない方が賢明です。
販売目的はもちろん、個人使用であっても最終的な責任はすべて自己責任となります。
実際のところ、市場には偽物のPSEマークがついた製品も少なからず流通しています。
見分け方を知らなければ、知らないうちに危険な製品を扱ってしまうリスクが高まります。
そこで、ここでは初心者でも実践できる、簡単で実用的なPSEマークの確認方法を紹介します。
PSEマークの形状やフォントを要チェック
正規のPSEマークは、丸型またはひし形のいずれかの形状で統一されており、
デザインのルールとして字体やサイズまで明確に規定されています。
これに対して偽物のPSEマークは、マークの形が歪んでいたり、
使用されているフォントが本来のものと異なっていたりすることが多いのが特徴です。
特に、素人が簡易的に作成したかのような粗雑な印字やバランスの悪いマークは要注意です。
公式に定められたデザインと見比べることで、こうした偽物特有の違和感に気づきやすくなります。
小さな差異を見逃さないことが、安全な製品を見極めるための第一歩です。
製造業者情報も要チェック
正規のPSEマークが付与された製品には、輸入事業者や製造事業者の情報が明確に表示されているのが基本です。
一方、偽物の製品ではこうした事業者情報がそもそも記載されていなかったり、
記載されていても実際には存在しない住所や連絡先が使われているケースが見受けられます。
これらの情報は、ネット検索で比較的簡単に確認できるため、必ずチェックすることが重要です。
正確で信頼できる事業者情報がしっかり記載されていることは、
その製品が安全性を満たしているかどうかを判断するうえで大きな安心材料となります。
正規の販売ルートが重要
偽物をつかまされないための最も確実な方法は、必ず正規の販売ルートを利用することです。
信頼性の高いメーカーや公式代理店を通して仕入れを行えば、偽物が紛れ込むリスクは大幅に下がります。
一方で、価格の安さだけに惹かれて正体のよくわからない業者から購入すると、
偽物や品質不良品をつかまされる危険が高まります。
特に初心者の方は、公式ストアや認定販売店といった信頼できる販売ルートを選ぶことが重要で、
この基本を守るだけでも多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
製品の外観・品質を要チェック
偽物の製品は、PSEマークだけでなく製品本体の作り自体が粗悪であることが少なくありません。
たとえば、プラスチック素材が極端に薄かったり、印字がかすれて読みにくかったり、
部品同士の組み立てが雑で隙間が目立つといった特徴が見られます。
実際に手に取ったときに全体的な質感が「安っぽい」と感じられる場合は特に注意が必要です。
正規品であれば細部の仕上げまで丁寧に作り込まれており、外観や触感からも一定の品質レベルが伝わってきます。
したがって、PSEマークの有無だけでなく、製品の品質全体をしっかり確認することが重要です。
本物の証明書があるかを確認
正規のPSE認証を受けた製品には、必ず試験報告書や適合証明書といった公式な書類が用意されています。
もし業者に問い合わせても、これらの証明書を提示できない場合は、その製品の信頼性に疑いを持つべきです。
また、証明書に記載されている製品の型番や仕様が、実際の製品と正確に一致しているかどうかも重要な確認ポイントです。
PSEマークの表示だけを見て安心するのではなく、
その裏付けとなる書類を必ずチェックする習慣を持つことで、安全性を確実に判断できます。
これは初心者でも実践できる、信頼性を見極めるための基本的な方法です。
まとめ

中国から電気製品を輸入して日本で販売する場合、PSEマークの取得は避けて通れない手続きです。
菱形PSEと丸形PSEの違いを理解し、自社が輸入する製品がどちらに該当するかを確認しましょう。
輸入業者自身が事業開始届を提出し、技術基準適合確認・試験・自主検査を経て、
PSEマークと輸入者名を表示することが法的に求められています。
さらに、偽物マークのチェックや販売時の注意点など、
正しい知識を持って安全な製品を届けることが重要です。
安全性を確保した上で、適切にPSEマークを取得・表示すれば、
日本市場で安心して家電製品を販売することができます。
本記事を参考に、手続きのポイントを押さえ、信頼できる製品を提供していきましょう。
ただし…PSEマークの闇…

ここまでPSEマークの重要性や認証取得・表示の方法について解説してきましたが、
正直なところPSEマークを取得したからといって、それ自体がビジネス上の強力な差別化要因になるわけではありません。
なぜなら、我々のように日本の法律を遵守し、真面目にPSE対応を進めたとしても、
海外の販売者の多くは日本の規制をほとんど意識していません。
PSEマーク無し、あるいは偽物のPSEマークを付けた製品を平然と販売しており、
仮にプラットフォームから垢バンや罰金を受けても、別名義で再出品するのが実態です。
この現実を踏まえると、真面目にPSE対策をしても不真面目な競合に価格やスピードで食われる可能性が高く、
むしろPSE不要の商品で戦略を立てた方がビジネス的には有利といえます。
PSE対象外の商品でも、アイデア次第で十分に利益を取れる商材は多く存在します。
私個人の見解としては、PSE対応は資本力のある大手企業が取り組むべき分野であり、
中小規模のプレイヤーはPSE不要のフィールドで勝ち筋を見つける方が賢明だと考えます。